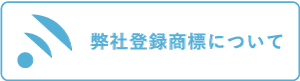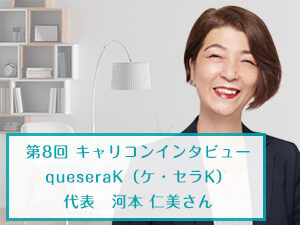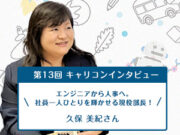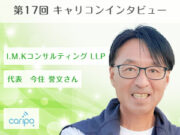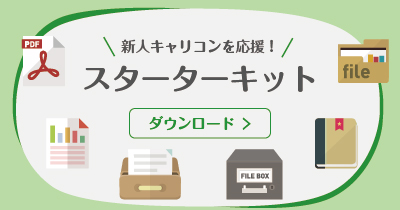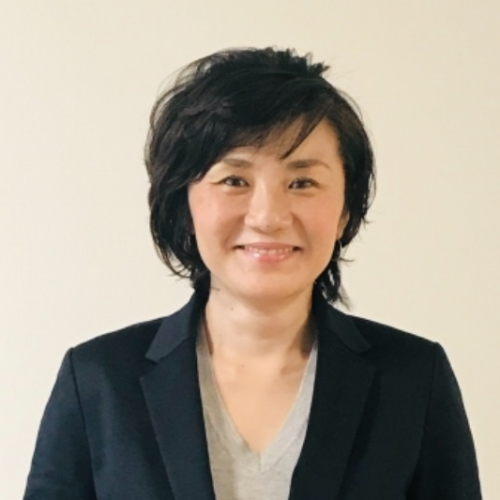
今回は、スターターキットの作成にもご協力いただいております、中部キャリアコンサルティング普及協会の中村 英泰さんにインタビューをさせていただきました。
キャリアコンサルティング技能士2級の資格もお持ちで、主に企業領域で活躍されている中村さんに、キャリコンサルタントとしての熱い思いを語っていただきました。
キャリアコンサルタント(以下、キャリコン)になる前の経歴を教えてください。
人材業界で、求職者の働きたいというウォンツと企業の働いてほしいというニーズを繋ぐ仕事をしていました。
主には、新規営業でニーズを増やすことと、働くスタッフのサポートです。
サポートと言うのは、スタッフから、退職したいという話があれば、より条件に合った仕事を繋いだり、不満があればそれをできるだけ詳しく聞いて改善できることは改善していくという内容です。
キャリコンの資格を取ろうと思ったきっかけは何ですか?
担当する派遣スタッフの数が100人規模に達したときから、仕事全体に限界を感じ始め、今までと違った何かいい方法がないかを模索している中で、キャリコンの資格(当時はCDA)を取ろうと思い立ちました。
キャリコンの資格を取ったことで何か変わったことはありますか?
取得前は、派遣会社側の視点で「売上や、契約件数、取引先との関係」を基に、派遣スタッフに“いかに長く勤めてもらうか?更新してもらうか?”を考えサポートをしていました。
取得後は【キャリア的視点】を持って「スタッフが、本当に困っているのは何か?」を考えてサポートすることができるようになったのが大きいですね。
こうして考えると、以前は完全に私視点でしたね。
資格取得後、キャリコンとして働いていくために、最初にどんな行動をしましたか?
資格取得直後から「将来はキャリコンを生業として生きていきたい」と思っていたので、在職中にキャリコンに関する仕事をアルバイト的に始めました。
当時は、社会的に今の様な副業と言うポジションは無かったので、隠れてコソコソ…的な感じでした。
具体的には、就職フェアのようなところで、外部のキャリコンとして相談に応じることや、派遣会社に勤めながら他の派遣会社が募集していた大学での学生に対する就活支援キャリコン(単発)の仕事もしましたね。
また、土日を利用して、キャリコン養成講座の運営スタッフもしました。
これらの仕事はどうやって探しましたか?
当時は、きゃりぽの様なサイトも無かったので、キャリコンが集まる勉強会に参加してリアルな交流を重ね「○○をしたい」みたいなことを色々な人に話していたことを憶えています。
そこから、少しずつご縁で、仕事を紹介してもらいましたね。